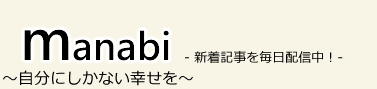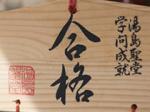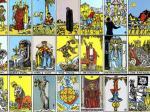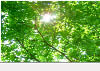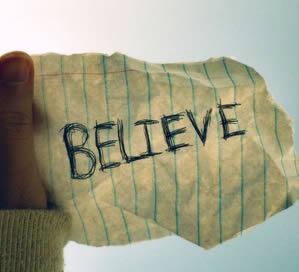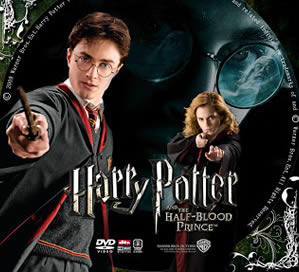社労士の資格
企業を経営するためには人・物・お金・情報という要素があり、「人」に関しては様々なことが絡みます。人についての問題は、人事や労働管理といった働く上での問題点だけでなく、少子・高齢化問題など社会現象も大きくかかわってきます。社会保険労務士は、企業の人事や労務管理全体にある問題部分を指摘し、改善策や安全策を助言します。そして少子・高齢化社会が大きく関わる医療保険や年金制度についての相談にも応じてくれる企業の強いパートナーです。
受験資格
- ①大学の一般教養科目の修了者または62単位以上の修得者、短大・高等専門学校(5年制)・修業年限2年以上の―部の専門学校の卒業者
- ②修業年限が2年以上で、課程修了に必要な総授業時間数が1700時間以上の司法試験験の第一を修了した者こよる次試験、旧司法試格した者
- ③司法試験予備試験、旧法規程よる司法試験験の第一試験、旧司法試験験の第一試験または高等試験予備試験に合格した者
- ④行政書士となる資格を有する者、弁理士・税理士・司法書士などの厚生労働大臣が認めた国家試験の合格者
- ⑤公務員として行政事務に通算して3年以上従事した者
- ⑥社会保険労務士もしくは社会保険労務士法人、または弁護士もしくは弁護士法人の業務の補助の事務に通算して3年以上従事した者
- ⑦労働組合または会社などの従業員として労働社会保険諸法令に関する事務に通算して3年以上従事した者
- ⑧全国社会保険労務士連合会の個別の受験資格審査により、学校教育法に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
試験日
受験料
試験地
- 北海道・岩手・宮城・山形・群馬・埼玉・東京・横浜・千葉・石川・静岡・愛知・京都・兵庫・大阪・岡山・広島・香川・福岡・熊本・沖縄
試験内容
- 『学科』
5肢択一式・70問と選択式8問
択一式試験は、各問1点とし1科目10点満点、合計70点満点
選択式試験は、各問1点とし1科目5点満点、合計40点満点
労働保険の保険料の徴収などに関する法律を除いた科目から出題
①労働基準法及び労働安全衛生法 ②労働者災害補償保険法(労災保険法)③雇用保険法 ④労務管理その他の労働に関する一般常識 ⑤社会保険に関する一般常識 ⑥健康保険法 ⑦厚生年金保険法 ③国民年金法
※択一式試験の試験科目のうち②③は、それぞれの問題10問のうち3問が「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」から出題される
合格率・難易度
- 第47回(2015年)
- 受験者数:40712人
- 合格率:2.7%
独学は難しい?
社会保険労務士の資格は合格率が5%以下と難関中の難関といえる資格ですが独学で取られている方もわずかながらいらっしゃるようです。独学のデメリットはご自身で情報収集を行ったりと受験対策が困難な点にあります。ただ費用面やご自身の都合に合わせて勉強できる利点もありますが、相当な覚悟がないと社労士を独学で取得するまでは難しいと言わざる得ないでしょう。
どれくらいの勉強時間が必要かというのは個人差がありますが、やはり1000時間単位でお考えになられる方が多いようです。
もし独学で取得されたいという方は月刊誌『社労士V』をおすすめします。独学にすべきか資格学校に迷われている方も一度読まれることでどちらを選択すべきかも見えてくるかと思います。
資格を取った後は?
社会保険労務士の仕事は書類作成、手続代行、コンサルティングの3つがメインです。書類作成と手続代行の業務がほとんどですが、コンサルティングに力を入れる社労士も近年増えています。企業が経営していく上での問題点を見つけ指摘し、改善する方向へと導いてくれ、なおかつコンサルティング面で頼れる社労士を多くの企業は求めています。労使関係のトラブルを抱える企業では、賃金制度を改定したり、就業規則を見直しする必要もあります。
どの部分が原因で問題が起きているのかをすばやく認識し解決に導いてくれるのは人事や労務の法律を専門とする社労士だからできることです。雇用形態も多様化し、ますます複雑になりつつあります。企業としても人事部門に人事、労務、社会保険の専門職を迎えたいところです。そういったことからもわかるように、社労士資格は就職には大きな武器です。資格を取得してれば資格手当を支給している企業もあります。独立開業せずに企業内社労士として勤務することで、社内で確固たる地位を築くこともできるでしょう。
ニーズが高い業種は銀行の年金相談窓口担当者、一般企業の労務管理責任者などです。しかし社労士資格を取得してまず考えるのは独立開業でしょう。独立開業する場合は、たくさんの企業と顧問契約を結ぶことで継続して顧問料を得ることができます。助成金申請などに注目をし、報酬を得ている社労士も近年では増えていますがスポット的業務がほとんどのため、ある程度安定した収入を望むなら顧問契約は欠かせません。
年金コンサルタントとしての仕事も現在では増えていますので、一般の人には理解しづらい複雑な年金の仕組みをしっかり把握することも大切です。社労士の資格を取得し社会保険労務士として登録した場合、紛争解決手続代理業務試験に合格することで紛争解決手続代理業務も行うことができます。他の専門分野では対応できない労務紛争に強い社労士は、弁護士からも頼りにされる存在になれます。
平均年収は?
平均月収は38万円、平均年収は男女によっても差があり、男性の平均年収は510万円ですが女性の平均年収は440万円くらいです。
関連の職業ページ
-
 生命保険外交員の給料は?≪仕事内容や報酬は?≫
生命保険外交員の給料は?≪仕事内容や報酬は?≫ 生命保険外交員は、新規契約が獲得できないストレスがあるのでしょうか?最初は既存顧客の引継ぎとかもあったり、新規で飛び込み営業や訪問…
-
 独身の保険は不要?いらない?
独身の保険は不要?いらない? 死亡した際の生命(死亡)保険は必要ないのか?それは被保険者(あなた)に経済的に支えられている人がいないからです。本来、生命保険は妻や子供がいる方が加入するものでご自身…
-
 コンプライアンスの資格≪企業や経営の資格を比較!≫
コンプライアンスの資格≪企業や経営の資格を比較!≫ 実践的な価値判断基準と法律的知識が備わっているかを判定する資格です。ここでコンプライアンスの有用とされる三つの資格をご紹介させていただきます…
-
 告知義務違反の時効や保険加入の審査とは?
告知義務違反の時効や保険加入の審査とは? 生命保険など契約を行った日から2年が経過した場合には保険会社は契約を解除することは出来ません。つまり加入時に持病などがあるにも関わらずそれを伝えず告知義務違反…
-
 文書処理の資格≪合格率や試験内容・文書処理能力検定≫
文書処理の資格≪合格率や試験内容・文書処理能力検定≫ 国語力、技術常識などの一般知識を持ち、ワープロや表計算を正確に迅速に扱える知識や実務能力があることを認定する資格です。1級の全問正解者には満点…
-
 税理士の仕事になるには?≪年収や仕事内容≫
税理士の仕事になるには?≪年収や仕事内容≫ 税務署は税金をチェックする組織です。税理士は決算など企業に為の役目があり様々な税金の納税義務があります。しかしながら、税金の法律はとても複雑でわかりにくい部分が多いのが現状です。税理士…
-
 公認会計士になるには≪仕事の年収や仕事内容≫
公認会計士になるには≪仕事の年収や仕事内容≫ 公認会計士になる為には公認会計士の資格試験に合格しなければなりません。その受験資格を得るための学歴や合格率…
-
 <a href="https://meigen.keiziban-jp.com/manabi/shigoto/syokugyou/financial/ァイナンシャルプランナーの仕事≪なるには?年収やFPの仕事内容≫
<a href="https://meigen.keiziban-jp.com/manabi/shigoto/syokugyou/financial/ァイナンシャルプランナーの仕事≪なるには?年収やFPの仕事内容≫ 仕事は個人や中小企業の相談に応じて、その資産に関する情報を収集、分析しファイナンシャルプランニングという資産計画を立ててアドバイスを行います…
この資格の勉強法や就職後など口コミを募集中!
 司法書士の仕事内容≪なるには?収入・給料は?≫ 様々な業務があります。最も重要な業務としては、登記業務があります。土地や建物の所有権を明確にするための不動産登記、会社を設立する際に必要な商業登記などがあります
司法書士の仕事内容≪なるには?収入・給料は?≫ 様々な業務があります。最も重要な業務としては、登記業務があります。土地や建物の所有権を明確にするための不動産登記、会社を設立する際に必要な商業登記などがあります  うつ病になると頭が回らない!記憶障害や記憶力の低下が起こる? 最初は何となくの抑うつ気分かなという感じですが、何も必要な対処をしなかったり以後も断続的に同じ状態が続くとどんどん悪化していく可能性。実際のところ、うつ病改善の為にこういった…
うつ病になると頭が回らない!記憶障害や記憶力の低下が起こる? 最初は何となくの抑うつ気分かなという感じですが、何も必要な対処をしなかったり以後も断続的に同じ状態が続くとどんどん悪化していく可能性。実際のところ、うつ病改善の為にこういった…  銀行の就職に必要な学歴≪学歴フィルターとは?≫ 地方銀行と”地方”を一括りで表現できませんが偏差値だけでいえばこの程度。ただし銀行はその銀行内部にどういったOBが多いか?コネクションは?と学歴以外も重要
銀行の就職に必要な学歴≪学歴フィルターとは?≫ 地方銀行と”地方”を一括りで表現できませんが偏差値だけでいえばこの程度。ただし銀行はその銀行内部にどういったOBが多いか?コネクションは?と学歴以外も重要  船長の仕事!船長になるには?≪年収や仕事内容≫ 船長にせよ実務経験が求められるので筆記のような試験だけでは船長にはなれません。年収で1000万円以上。某海運会社の船長は月収30万円~。空いた時間に事務仕事を行うため
船長の仕事!船長になるには?≪年収や仕事内容≫ 船長にせよ実務経験が求められるので筆記のような試験だけでは船長にはなれません。年収で1000万円以上。某海運会社の船長は月収30万円~。空いた時間に事務仕事を行うため  ロト6で1等の高額当選が出た宝くじ売り場≪香川・徳島・高知・愛媛≫ 売場前で当選祈願を行っている大変ありがたい売り場。これが話題となりマスコミでも多く取り上げられて大盛況となっているとのこと。やはり宝くじの醍醐味は一攫千金であることは間違いありません…
ロト6で1等の高額当選が出た宝くじ売り場≪香川・徳島・高知・愛媛≫ 売場前で当選祈願を行っている大変ありがたい売り場。これが話題となりマスコミでも多く取り上げられて大盛況となっているとのこと。やはり宝くじの醍醐味は一攫千金であることは間違いありません…  少彦名神社の御朱印や駐車場≪お守りや限定御朱印帳≫ 楽しめて時間を忘れるとにかく観光を満喫できるエリアで、一日では物足りないかもしれません。そんな病気平癒のご神徳がある少彦名神社があり限定御朱印帳や御朱印からお守りも購入でき…
少彦名神社の御朱印や駐車場≪お守りや限定御朱印帳≫ 楽しめて時間を忘れるとにかく観光を満喫できるエリアで、一日では物足りないかもしれません。そんな病気平癒のご神徳がある少彦名神社があり限定御朱印帳や御朱印からお守りも購入でき…  住吉神社(福岡)ご利益や無料駐車場≪おみくじ≫ お正月は1回500円程度かかったと思います。また全ての災いから身を守るご利益、縁結びのご利益があると言われています。ここでは住吉神社(福岡)、ご利益や無料駐車場、おみくじ…
住吉神社(福岡)ご利益や無料駐車場≪おみくじ≫ お正月は1回500円程度かかったと思います。また全ての災いから身を守るご利益、縁結びのご利益があると言われています。ここでは住吉神社(福岡)、ご利益や無料駐車場、おみくじ…  造園技能士の年収は?合格率や受験資格は? 実際に庭園を作成する作業試験と樹木の枝を見て樹木名を判定する要素試験があり、これらすべてに合格して、初めて造園技能士の資格…
造園技能士の年収は?合格率や受験資格は? 実際に庭園を作成する作業試験と樹木の枝を見て樹木名を判定する要素試験があり、これらすべてに合格して、初めて造園技能士の資格…  大使になるには?大使館で働くには?≪年収や仕事内容≫ 滞在先国での日本広報活動、外交、政治や経済、外交面などの情報を収集する事などに分けられます。任務に就く国は日本大使館を置いている国や地域であり、それらすべてに大使
大使になるには?大使館で働くには?≪年収や仕事内容≫ 滞在先国での日本広報活動、外交、政治や経済、外交面などの情報を収集する事などに分けられます。任務に就く国は日本大使館を置いている国や地域であり、それらすべてに大使  片思いを諦める方法は?職場恋愛を忘れるには? 同じ職場だと、片想いを諦めるため彼のことを忘れようと距離を置くことはできません。仕事仲間ゆえ会社で毎日顔を合わせなければならず、逆にその想いは募るばかりです。どうしても諦めきれない…
片思いを諦める方法は?職場恋愛を忘れるには? 同じ職場だと、片想いを諦めるため彼のことを忘れようと距離を置くことはできません。仕事仲間ゆえ会社で毎日顔を合わせなければならず、逆にその想いは募るばかりです。どうしても諦めきれない…  よく当たる宝くじ売り場≪長野≫ 周辺施設には、ゆいが三郷店や、カインズホーム等があり、最寄り駅はJR梓橋駅(大糸線)になります。イトーヨーカドー甲府昭和店にあります。群馬と続き、こちらもまた注目すべき強運
よく当たる宝くじ売り場≪長野≫ 周辺施設には、ゆいが三郷店や、カインズホーム等があり、最寄り駅はJR梓橋駅(大糸線)になります。イトーヨーカドー甲府昭和店にあります。群馬と続き、こちらもまた注目すべき強運  厄払い神社や厄除け祈願≪富山県≫ 利長の意向により、慶長年間に現在地に移ったとされています。総持寺は別名「すずらん寺」とも呼ばれていて春には境内にすずらんが一面… 厄除け、合格などのご利益を賜ることが出来ますので参拝に…
厄払い神社や厄除け祈願≪富山県≫ 利長の意向により、慶長年間に現在地に移ったとされています。総持寺は別名「すずらん寺」とも呼ばれていて春には境内にすずらんが一面… 厄除け、合格などのご利益を賜ることが出来ますので参拝に…  縁起のいい財布とは?風水の良い財布≪2026年≫ 材質が大切です。ボロボロになって汚れたお財布を長く使っていて金運がアップする感覚を持てませんよね。そういう意味で生活スタイルや普段…
縁起のいい財布とは?風水の良い財布≪2026年≫ 材質が大切です。ボロボロになって汚れたお財布を長く使っていて金運がアップする感覚を持てませんよね。そういう意味で生活スタイルや普段…  株価の見通し(2015年)~世界の投資家の「夢」と不安~ 欧州も成長が上方修正されたのですから株価が上昇してもおかしくないのですが、新値を更新するほどの上昇は観察されません…
株価の見通し(2015年)~世界の投資家の「夢」と不安~ 欧州も成長が上方修正されたのですから株価が上昇してもおかしくないのですが、新値を更新するほどの上昇は観察されません…  漢字の資格≪日本漢宇能力検定(漢検)の合格率や難易度≫ 活字についての検定など漢検は友達などと一緒に受検するケースも多く学習習慣も身につけられます。また2015年度の入試では、大学・短大のうちなんと45%もの大学・短期
漢字の資格≪日本漢宇能力検定(漢検)の合格率や難易度≫ 活字についての検定など漢検は友達などと一緒に受検するケースも多く学習習慣も身につけられます。また2015年度の入試では、大学・短大のうちなんと45%もの大学・短期  CGデザイナーの資格や将来性は?≪やりがいや給料や仕事内容≫ どんな仕事も毎日楽しく、常に成果が出るわけではありません。どんな職業でも表で活躍する方の裏には素晴らしい方々の支えや作業…
CGデザイナーの資格や将来性は?≪やりがいや給料や仕事内容≫ どんな仕事も毎日楽しく、常に成果が出るわけではありません。どんな職業でも表で活躍する方の裏には素晴らしい方々の支えや作業…  テストステロンとうつ病の発症≪実体験談!≫ 減少が進むと高血圧や内蔵脂肪の増加(メタボ)などの体の変化が起こり、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高めるようで、加齢と共にテストステロン値は減少するようですが、かなり個人差があるらしく…
テストステロンとうつ病の発症≪実体験談!≫ 減少が進むと高血圧や内蔵脂肪の増加(メタボ)などの体の変化が起こり、心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高めるようで、加齢と共にテストステロン値は減少するようですが、かなり個人差があるらしく…