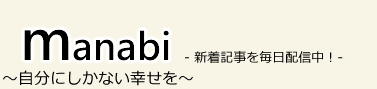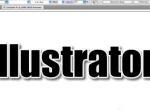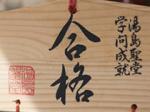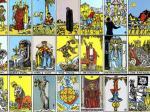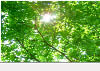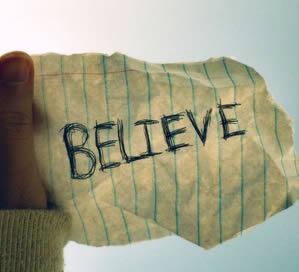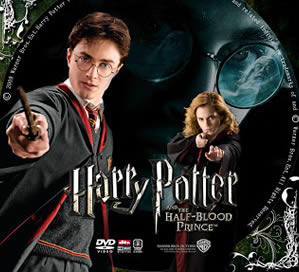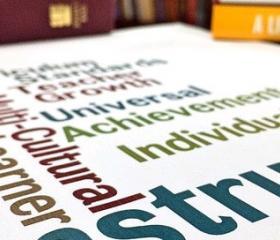どんな仕事?
保護司の使命は、罪を犯した人や非行のある少年が円滑に社会復帰できるように、犯罪や非行を予防しながら福祉に寄与することです。罪を犯した人や非行のある少年に対して保護観察官と連携しながらの指導やアドバイス、地域社会の犯罪予防活動を行います。非常勤の国家公務員ですが給与の支給はされないため、実質的には民間のボランティアですが活動内容に応じて、一定の実費弁償金が支給されます。
選考基準や資格
保護司になるための資格は特に必要ありませんが保護観察所の長が各保護観察所に置かねた保護司選考会(地方裁半」所長、地方検察庁検事正、弁護士会長などで構成)に意見を聞いたうえで、推薦した者の中から法務大臣が委嘱する。任期は2年間だが再任されることもできます。
【保護司には以下の条件を備えていることが必要】
①人格・行動について社会的信望を有する
②職務の遂行に必要な熱意・時間的余裕を有する
③生活が安定している
④健康で活動力を有する
申し込み方法
各都道府県の保護観察所にお問い合わせ下さい。
保護司になれない人
■ 成年被後見人又は被保佐人
■ 禁錮以上の刑に処せられた者
■ 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
年齢
保護司になる為の年齢制限は特に明確に定められておりません。
研修内容
保護司になると、経験年数や適性に応じて各種の研修を受講します。
- ①新任保護司研修:すべての新任保護司が対象。保護司の使命・役害」・身分など、保護司として必要な基礎的知識・心構えの修得を図る
- ②処遇基礎力強化研修(第一次研修):初めて保護司を委嘱された者が対象。保護司の職務遂行に必要な事務手続きや処遇実務の具体的履修、保護司会活動についての理解促進を図る
- ③指導力強化研修(第二次研修)i初めて再任された2期目の保護司が研修内容 対象。保護観察等の処遇を行ううえで必要な知識 技術の伸長、保護司会活動を行ううえで必要な知識 技術の修得を図り、処遇や保護司会活動などにおいて、中核的な役割を担うための指導力を身につける
- ④地域別定例研修:保護司全員が対象。保護区ことに実施する研修で実務上必要な知識・技術の全般的な水準向上を図る
- ⑤特別研修:処遇上特別な配慮を必要とする者の取り扱いなどに関する専門的知識・技術の修得を図る
- ⑥自主研修:各保護司会などにおける自主的な研修
活動
保護司は、法務大臣からの委嘱を受けた非常勤の国家公務員です。保護司法の規定に基づいて、都道府県の保護区のいずれかに所属することになります。
罪を犯した人や非行のある少年と定期的に面接を行って、更生するための約束事を守るように指導し、アドバイスや就労のサポートを行います。
釈放された後に社会に円滑な復帰ができるように、帰住予定地の調査や身元引受人との話合い等を行って受け入れ態勢を整備します。
犯罪や非行を防ぎ、罪を犯した人を更生することへの理解を深めて世論の啓発・地域社会の浄化を活動としています。
報酬
保護司の報酬は保護司実費弁償金支給規則に基づいて支払われます。下記は規則ですが文言をシンプルにまとめております。
- 第一条:保護司法第十一条第二項の規定により保護司に支給すべき費用についてはこの規則の定めるところによる
- (補導費)第二条:保護司が保護観察を担当したときは担当事件一件につき一箇月七千五百二十円以内の費用を支給
- (生活環境調整費)第三条:保護司が保護観察所長から生活環境の調整又は保護観察に関する調査(以下「生活環境調整等」という。)を命ぜられ、その結果を報告したときは一件につき三千三百七十円以内の費用を支給する。ただし、生活環境調整等の場所が保護司の居住地から片道八キロメートル以上の場合には、これに要した旅行実費を支給。
- (特殊事務処理費)第四条:保護司が保護観察所長から裁判所、検察庁等との連絡その他特殊の事務を処理するものとしてあらかじめ指名を受け、その事務を処理したときは、一日六千六百円以内の費用を支給する。
- (その他の費用)第五条:保護司が前三条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認めこれを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。
- (旅行実費の算出)第六条:第三条及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定により行うものとし、職務の級については一般職の職員の給与に関する法律に規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各保護司につき、別に法務大臣が定める職務の級にあるものとして計算
身の危険
犯罪を起こし保護観察処分となった場合、少年一人一人に保護観察官が付くわけですが、見守りは保護司が担当します。
保護司をされている方のやりがいは更生していく姿を見るのが嬉しい、やりがいというご回答が多いですが身の危険を感じることはどうなのでしょう?
保護司になるのとならないとでどちらが安全かといえば、当然やらないという選択はそういう人物と接することがないのでやらない方が安全でしょう。
ただ保護司一人がその人物に接して全ての責任を負うわけではなく地域によっては児童相談所、教育委員会などと連携、共有をしている場合もあるので、逆恨みや危害を加えられるといったことはほとんどないのが現状です。
関連の職業ページ
-
 児童相談員になるには?≪児童福祉司の給料や年収や仕事内容≫
児童相談員になるには?≪児童福祉司の給料や年収や仕事内容≫ 児童相談員の就職先は様々な施設があります…。臨床心理士などの資格は希望者がたくさんいるので競争率は高い水準で推移…。四年制の大学に…
-
 ケースワーカー(福祉事務所)になるには?≪給料や学歴は?≫
ケースワーカー(福祉事務所)になるには?≪給料や学歴は?≫ 大学や短大では厚生労働省の指定科目のうち、3科目を…、医療法人が運営する病院のケースワーカーは、その医療法人が雇ったスタッフです。…
-
 臨床美術士の資格≪芸術療法の収入や就職の大学≫
臨床美術士の資格≪芸術療法の収入や就職の大学≫ 臨床美術は主に認知症高齢者、MCI(前認知症の人)、心に問題を抱えた子供や発達が気になる子供、子供の感性教育、一般社会人のメンタルヘルスケアなどを対象に実施…
-
 ケアワーカーの仕事内容≪資格や給料や種類は?≫
ケアワーカーの仕事内容≪資格や給料や種類は?≫ 実はケアワーカーというのは広い範囲の職業を指します。まずCare(ケア)とは看護、養護、配慮という意味になりWorkerとは仕事をする人ですから、看護や養護の仕事をする人になり…
-
 僧侶になるには?≪資格や収入や仕事内容≫
僧侶になるには?≪資格や収入や仕事内容≫ 僧侶になる方法はそれぞれのお寺が研修僧を募集しているものに応募をする方法があります。募集要項はお寺によって違うので仏教…
-
 社会教育主事の給料や年収≪仕事や資格≫
社会教育主事の給料や年収≪仕事や資格≫ どういう場所なのか?また詳しい業務や報酬体系は?社会教育の現場だと1年の現場経験で資格になると聞いたのですが、具体的に社会教育の現場…
-
 認知症ケア専門士の受験資格≪問題集や合格率≫
認知症ケア専門士の受験資格≪問題集や合格率≫ 認知症ケア専門士は高齢の方が比較的多い仕事。介護施設は介護職員の不明瞭な行為があると入居を拒否される…
この資格の勉強法や就職後など口コミを募集中!
 プログラマーの給料≪なるには?資格や大学や未経験は?≫ プログラマーの仕事は、プログラム言語を用いてプログラムを組む。プログラマーになる為にはどういった大学・学部に進めば良いかというとコンピュータサイエンス学部、情報システム系情報技術科…
プログラマーの給料≪なるには?資格や大学や未経験は?≫ プログラマーの仕事は、プログラム言語を用いてプログラムを組む。プログラマーになる為にはどういった大学・学部に進めば良いかというとコンピュータサイエンス学部、情報システム系情報技術科…  環境NGO NPOスタッフになるには?≪年収や仕事内容≫ 国内問題だけでは無く、海外や地球規模での問題に対して環境改善や創生、再生、対策などの取り組みを行っています。国内NPOに始まり、海外に本社があり、世界各国に法人を置き
環境NGO NPOスタッフになるには?≪年収や仕事内容≫ 国内問題だけでは無く、海外や地球規模での問題に対して環境改善や創生、再生、対策などの取り組みを行っています。国内NPOに始まり、海外に本社があり、世界各国に法人を置き  宝くじ当たる夢を見て高額当選した!≪正夢だった!≫ その数日後に大洪水に巻き込まれて家から逃げ出したら、なぜか清流にたどり着くという夢を見られたようで、このOさんには宝くじで2億円当選させたKさんという知人がいるらしく、その夢の事を話し…
宝くじ当たる夢を見て高額当選した!≪正夢だった!≫ その数日後に大洪水に巻き込まれて家から逃げ出したら、なぜか清流にたどり着くという夢を見られたようで、このOさんには宝くじで2億円当選させたKさんという知人がいるらしく、その夢の事を話し…  指揮者の年収は?≪有名になるには?大学や最短ルート≫ 指揮者になる為には、やはり音楽大学や芸大の音楽学部、指揮科などへ進む必要があります。しかし音楽大学の指揮科に入るのには…
指揮者の年収は?≪有名になるには?大学や最短ルート≫ 指揮者になる為には、やはり音楽大学や芸大の音楽学部、指揮科などへ進む必要があります。しかし音楽大学の指揮科に入るのには…  石切神社の「お百度参り」やり方≪効果や守るべきルールとは?≫ いつ治るか分からない、本当に完治するかどうかも分からない暗闇に入り込んでしまうと毎日不安になるものですよね。病で辛い思いをされている方は一日も早く全快されることを願っております。病気平癒…
石切神社の「お百度参り」やり方≪効果や守るべきルールとは?≫ いつ治るか分からない、本当に完治するかどうかも分からない暗闇に入り込んでしまうと毎日不安になるものですよね。病で辛い思いをされている方は一日も早く全快されることを願っております。病気平癒…  支えてくれる女性の意味は?≪男性の感謝≫ 恋愛でも結婚生活でもそうですが、お互いの人としての成熟度に大きな差が生まれてくるとズレが生じてきてしまい関係悪化を招きやすいです。やはり人間に…
支えてくれる女性の意味は?≪男性の感謝≫ 恋愛でも結婚生活でもそうですが、お互いの人としての成熟度に大きな差が生まれてくるとズレが生じてきてしまい関係悪化を招きやすいです。やはり人間に…  うつ病になると頭が回らない!記憶障害や記憶力の低下が起こる? 最初は何となくの抑うつ気分かなという感じですが、何も必要な対処をしなかったり以後も断続的に同じ状態が続くとどんどん悪化していく可能性。実際のところ、うつ病改善の為にこういった…
うつ病になると頭が回らない!記憶障害や記憶力の低下が起こる? 最初は何となくの抑うつ気分かなという感じですが、何も必要な対処をしなかったり以後も断続的に同じ状態が続くとどんどん悪化していく可能性。実際のところ、うつ病改善の為にこういった…  郵便局員の年収や給料は?≪郵便局で働くには?≫ 「日本郵便株式会社」となりました。日本郵政グループの一般職やサービス職が郵便局員に該当します。局員の郵便業務の具体的な仕事…
郵便局員の年収や給料は?≪郵便局で働くには?≫ 「日本郵便株式会社」となりました。日本郵政グループの一般職やサービス職が郵便局員に該当します。局員の郵便業務の具体的な仕事…  脳梗塞の神社≪うつ病や頭痛や脳の病気の宇賀部神社!≫ 「おこべじんじゃ」或いは「おこべさん」の愛称で親しまれていますが、正式な名称は「うかべじんじゃ」です。ご利益は頭の神様ですので、特に首から上の病気平癒(頭、目、鼻、耳、口、喉、首の病気…
脳梗塞の神社≪うつ病や頭痛や脳の病気の宇賀部神社!≫ 「おこべじんじゃ」或いは「おこべさん」の愛称で親しまれていますが、正式な名称は「うかべじんじゃ」です。ご利益は頭の神様ですので、特に首から上の病気平癒(頭、目、鼻、耳、口、喉、首の病気…  厄払い神社や有名な厄除け祈願の神社≪全国対応≫ 神産巣日神と天照大神が祀られています。伊弉諾尊と伊弉册尊のお使いとされている狼は御眷属様と呼ばれ、あらゆるものを祓い清め、様々な災いを除くので本当に効果が高いと評判になっています…
厄払い神社や有名な厄除け祈願の神社≪全国対応≫ 神産巣日神と天照大神が祀られています。伊弉諾尊と伊弉册尊のお使いとされている狼は御眷属様と呼ばれ、あらゆるものを祓い清め、様々な災いを除くので本当に効果が高いと評判になっています…  明治神宮の効果は?≪東京の金運の最強スポット!≫ 東京都渋谷区にある明治神宮です。初詣では例年日本一の参拝者数を誇る神社で、人が賑わうところご利益有りということで金運アップ効果もあると言われています。また明治神宮は明治天皇と昭憲皇太后…
明治神宮の効果は?≪東京の金運の最強スポット!≫ 東京都渋谷区にある明治神宮です。初詣では例年日本一の参拝者数を誇る神社で、人が賑わうところご利益有りということで金運アップ効果もあると言われています。また明治神宮は明治天皇と昭憲皇太后…  陶芸家になるには?≪収入やプロとして有名になる方法は?≫ 自分の作品を売るだけで生計を立てることはなかなか難しく、自分の作品作りと並行して、依頼される物を作ったり、陶芸教室などを開いて…
陶芸家になるには?≪収入やプロとして有名になる方法は?≫ 自分の作品を売るだけで生計を立てることはなかなか難しく、自分の作品作りと並行して、依頼される物を作ったり、陶芸教室などを開いて…  食育インストラクターの資格≪費用や独学≫ NPO日本食育インストラクター協会と全国調理師養成施設協会の二つの資格をご紹介させていただきます。※どちらの資格も民間資格…
食育インストラクターの資格≪費用や独学≫ NPO日本食育インストラクター協会と全国調理師養成施設協会の二つの資格をご紹介させていただきます。※どちらの資格も民間資格…  ショコラティエになるには?≪資格や年収・仕事内容・学歴は?≫ ショコラティエは、チョコレート専門のお菓子を作ることが仕事です。洋菓子職人としてパティシエがいますが、パティシエはお菓子全般を学び洋菓子と一緒
ショコラティエになるには?≪資格や年収・仕事内容・学歴は?≫ ショコラティエは、チョコレート専門のお菓子を作ることが仕事です。洋菓子職人としてパティシエがいますが、パティシエはお菓子全般を学び洋菓子と一緒  うつ病の時に暗い部屋に居るのは良い事?ダメな事? 一人では寂しいので家族がいる実家が良いという方もいれば、家事の音、家族の雑談の音や内容が気になるので、一人で居たいという方もいます。また部屋に差す光が辛いので、暗い部屋が落ち着くという方…
うつ病の時に暗い部屋に居るのは良い事?ダメな事? 一人では寂しいので家族がいる実家が良いという方もいれば、家事の音、家族の雑談の音や内容が気になるので、一人で居たいという方もいます。また部屋に差す光が辛いので、暗い部屋が落ち着くという方…  伊勢神宮の御朱印や時間≪場所や料金や御朱印帳も!≫ 興味がない人でも知っていることでしょう。年間の参拝者数が800万人超えということで、外国人観光客も数多く見かけます。伊勢神宮には素晴らしい御朱印帳も頒布されており、場所や値段…
伊勢神宮の御朱印や時間≪場所や料金や御朱印帳も!≫ 興味がない人でも知っていることでしょう。年間の参拝者数が800万人超えということで、外国人観光客も数多く見かけます。伊勢神宮には素晴らしい御朱印帳も頒布されており、場所や値段…  広島護国神社の御朱印や時間≪無料駐車場や限定御朱印帳!≫ 広島市といえば思い浮かぶのが原爆ドームや平和記念公園ですが、それ以外にマツダスタジアムもあります。広島市に鎮座しているのが広島護国神社で御朱印や受付時間、無料駐車場から御朱印帳…
広島護国神社の御朱印や時間≪無料駐車場や限定御朱印帳!≫ 広島市といえば思い浮かぶのが原爆ドームや平和記念公園ですが、それ以外にマツダスタジアムもあります。広島市に鎮座しているのが広島護国神社で御朱印や受付時間、無料駐車場から御朱印帳…